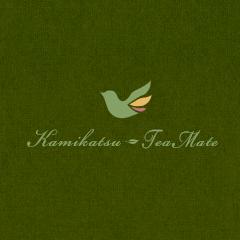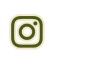阿波晩茶は、手間のかかる発酵茶です。
7〜8月の短い期間に、茶摘み、茶茹で、茶摺り、漬け込み、天日干し、選別まで進み、多くが手作業で、昔ながらの道具が使われてきたと説明されています。
だからこそ、続けるには覚悟が要ります。
一方で、続けるためには“工夫”も必要です。
この回では、阿波晩茶農家が誇りを保ちながら、どんな課題に向き合い、どう未来へ渡そうとしているのかを、できるだけ具体的に整理します。
1. 夏の集中作業は、体力だけではない「総合力」の仕事
阿波晩茶づくりは夏に集中します。手摘みで数日から場合によっては二週間以上かかることがある、という説明もあり、作業量の大きさがうかがえます。
そして仕込みの日は、茶茹で、茶摺り、漬け込みを一日で行う流れが示されています。
この工程は、力仕事であると同時に、段取りの仕事です。
釜の火、湯の状態、茶葉の扱い、摺りの加減、踏み込みの密度、密閉の確実さ。発酵の方向性は、こうした積み重ねで決まります。嫌気的に乳酸発酵を促すために、空気を抜く意図が工程として説明されているように、理屈が分かったうえで“所作”が必要になります。
農家が誇りを持つのは、毎年の条件が違っても、家の味として成立させる総合力を持っているからです。単に古い方法を残しているのではなく、毎年「今年の茶」を見て、同じ本質に着地させる。これは熟練の技術です。
2. 木桶、茶摺り舟、竈――道具を守ることは、文化を守ること
阿波晩茶の工程では、巨大な木製桶に漬け込み、踏み込んで密封し、重石を積むといった手法が説明されています。
また、茶摺りでは「茶摺り舟」を使った手作業が続けられているとされます。
これらの道具は、単なる器具ではありません。
道具があるから工程が成立し、工程があるから技術が伝わり、技術があるから味と文化が残る。つまり道具は、伝統の“記憶媒体”です。
しかし木桶は手入れが必要です。保管の仕方ひとつで寿命が変わります。茶摺り舟も、使い続けるほどに手になじみます。竈や釜周りも、現代の設備とは違う癖があります。
だから農家は、茶葉だけでなく、道具も守っている。ここに、伝統を守る誇りの具体があります。
3. 重要無形民俗文化財の指定は「続ける理由」を社会と共有する装置
阿波晩茶の製造技術が、上勝町・那賀町・美波町などに伝承される民俗技術として重要無形民俗文化財に指定されたことは、行政資料でも確認できます。
指定の意義は、外からの評価というより、内側の人たちの「続ける理由」が言葉になった点にあります。
伝統は、当事者だけの努力では維持が難しい局面が必ず来ます。
手間がかかる、収量が安定しない、担い手が減る、生活様式が変わる。そうした波の中で、指定は「これは地域にとって残す価値がある」という合意形成を助けます。
そして、保存会などの枠組みが明示されていることも大きい。
個人の努力だけでなく、地域の仕組みとして守る段階へ。ここで農家の誇りは、個人の腕前から「共同体としての継承」へと広がっていきます。
4. “家の味”を守りながら、外の世界へ伝える難しさ
阿波晩茶は、家ごとに自給中心で作られてきたという背景があります。
これは大きな魅力である一方、外へ伝えるときに難しさも生みます。なぜなら、画一的な正解がないからです。
伝統を守り抜く誇りとは、「唯一の正解を押しつけること」ではなく、家ごとの違いを尊重しながら、本質を共有することです。たとえば本質は次のような要素に整理できます。
-
盛夏に成長した葉を使うという季節性
-
茶葉を茹で、摺って傷をつける工程の意味
-
木桶に漬け込み、空気を抜いて嫌気的に乳酸発酵を促すという考え方
-
天日干しと選別まで含めて品質を仕上げる手仕事
この本質を外部に丁寧に説明できることが、伝統を未来へ渡すうえで重要になっていきます。
5. 未来へ渡すための現代的な工夫:誇りを折らない「続け方」
伝統は、精神論だけでは続きません。
阿波晩茶農家が誇りを守り抜くには、「続けられる形」に整える工夫が不可欠です。ここでは一般論として、伝統の本質を損なわずに取り入れやすい工夫を挙げます。
(1)工程の見える化と記録
発酵は目に見えにくいからこそ、気温、仕込み日、桶の状態、発酵期間、干しの条件などを記録しておくことで、経験の共有がしやすくなります。これは家の味を消すためではなく、次の世代が学ぶための土台になります。
(2)安全と衛生の基本を整える
伝統的工程の核心は「木桶での嫌気発酵」や「茶摺り舟の手仕事」にあります。
その核心を守りながら、作業場の整理や清掃、乾燥場所の管理など、現代的な衛生の基礎を整えることは、外部に伝える際の信頼にもつながります。
(3)共同作業の再構築
茶摘みは家族や親類が中心で、必要に応じて近所や知人の手も借りるとされます。
この“助け合い”を、無理のない形で続けることが、担い手不足への現実的な対策になり得ます。手伝いが入る日を決める、役割を分ける、道具の共有ルールを作るなど、コミュニティ設計が鍵になります。
(4)体験や対話で価値を伝える
阿波晩茶は、製法を知るほど味の感じ方が変わるお茶です。
摘む、茹でる、摺る、漬ける、干す――工程の意味を伝えることで、飲み手は「安さ」ではなく「背景」に価値を見出すようになります。結果として、伝統が経済的にも支えられやすくなります。
6. 農家の誇りの核心は、「自分の代で途切れさせない」覚悟
重要無形民俗文化財に指定されたという事実は、外側からの光です。
けれど最後に伝統を守るのは、毎年夏に茶葉を摘み、釜の前に立ち、茶を摺り、桶に漬け、干し上げる人の手です。
「今年も作れた」という小さな達成が積み重なり、伝統はつながっていきます。
誇りとは、過去を飾る言葉ではなく、暑い季節にもう一度立ち上がる力です。家の味を守りながら、地域の文化として次へ渡す。その覚悟が、阿波晩茶農家の背骨になっています。
伝統を守る誇りは、変えずに残すことではなく、続けられる形で渡すこと
阿波晩茶は、盛夏の葉を摘み、茹で、摺り、木桶に漬け、嫌気的に乳酸発酵を促し、天日干しと選別で仕上げるという、他に類例の少ない伝統技術として評価されてきました。
そしてその技術は、重要無形民俗文化財として、地域の文化そのものとして位置づけられています。
誇りは、守り抜くための工夫と一体です。
今年も作り、来年へ渡す。人と道具と山里の季節を、途切れさせない。
阿波晩茶農家の誇りは、その静かな継続の中にあります。