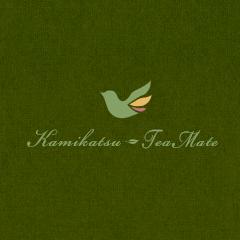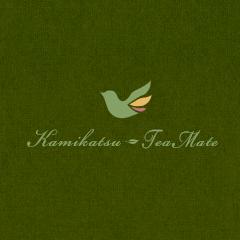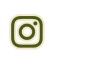皆さんこんにちは!
Kamikatsu-TeaMateの更新担当の中西です!
さて今日は
未来に繋ぐ阿波晩茶〜episode19〜
徳島県の山あいで受け継がれてきた乳酸発酵茶「阿波晩茶」。2021年に国の重要無形民俗文化財に指定され、全国から関心が高まっています。どんなサイクルで育ち、いつ摘むのが“旬”なのか。現地資料と作り手の声をもとに、育成期間と茶摘み時期を中心にまとめました。
阿波晩茶の一年:育てて、盛夏に摘む
「晩茶(ばんちゃ)」の名は、**“遅い時期に摘む”**ことに由来。夏の葉を使う独自の製法が、名称にも刻まれています。
なぜ“夏摘み”なの?——阿波晩茶が育つ理由
阿波晩茶は、摘採 → 茹でる → 擦る(茶摺り) → 木桶に漬けて乳酸発酵 → 天日干しという工程で作られます。発酵を促すには厚手で繊維質のしっかりした葉が向き、気温が高い盛夏は乳酸菌が働きやすい。だからこそ“夏に育て、夏に摘む”のです。
地域の気候と地形:山の暮らしが育てる茶
主な産地は、徳島県上勝町・那賀町・美波町などの山間部。標高数百メートルの斜面畑で、家ごとに自給中心の小さな単位で受け継がれてきました。山の気候(昼夜の寒暖、夏の高温)と作業環境が、**“夏摘み・発酵”**という個性を支えています。
作り手のカレンダー(目安)
取材記では、7月中旬に上勝町で茶摘み〜漬け込みまでの工程を行い、後日「桶出し→干し→選別」と進める例が紹介されています。盛夏の作業であることがよくわかります。
収穫の“見極めポイント”——現場の目安
-
葉の厚み・硬さ:薄い若葉は香味は良くても発酵に不向き。厚みとコシが出る夏葉が本命。
-
天候:漬け込み期は高温が望ましく、乾燥期は晴天が欲しい。作柄は気象の影響を強く受けます
-
畑の位置:山間部では日当たりや標高差で時期がずれるため、同じ町内でも摘み始めが前後します。
もう一歩深く:阿波晩茶の“いま”
まとめ:阿波晩茶は「夏を摘む茶」
-
育成期間:春に芽吹かせ、夏まで育てる(春は摘まない)。
-
茶摘み時期:6月下旬〜8月上旬が中心、ピークは7月。厚手の葉を手摘みで収穫。
-
理由:厚葉×高温が、桶の中での乳酸発酵を助け、独特の酸味と香りを生む。
“春に摘まない勇気”と“夏に働く発酵の力”。この二つが重なって、阿波晩茶の季節は出来上がります。次の夏、産地の空気を想像しながら一杯いれてみてください。盛夏の山の匂いと、静かな旨みが、湯気の向こうからやってきます。
阿波晩茶はオンラインでもご購入できます♪
オンラインショップ