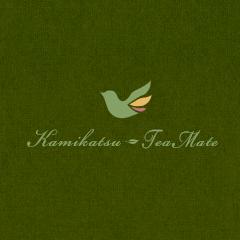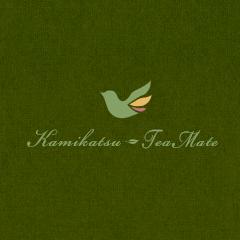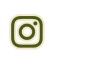皆さんこんにちは!
Kamikatsu-TeaMateの更新担当の中西です!
さて今日は
未来に繋ぐ阿波晩茶〜地域復興へ向けて2〜
ということで、現在、上勝町で行っている地域復興へ向けた取り組みについてご紹介いたします♪
徳島県上勝町。山間の静かな集落で代々受け継がれてきた“在来茶”の文化が、今、新たな岐路に立っています。
高齢化や後継者不足の中、ある茶農家は「次の世代」にこの文化と山をつなげるために、暮らし・体験・創造をキーワードにした新しい取り組みを始めています。
1. 茶畑に「人を呼ぶ」:田舎暮らしと就農体験
上勝町では、単なる農業研修ではなく、“暮らしとともに茶を知る”体験型プログラムを導入しています。
■ 取り組みの特徴
-
茶摘みや製茶だけでなく、地域の山仕事・暮らしの知恵も一緒に学ぶ
-
空き家を活用した短期滞在型の就農体験で、生活のリアルを体感
-
地元住民と「食卓を囲む」時間を設け、地域に根ざした関係を築く
→ 都市から来た若者にとって、「農業=労働」ではなく「生き方の選択肢」として捉え直す機会に。
■ 成果と課題
-
実際に移住・就農につながった若者も誕生
-
一方で、収入確保や販路の整備が今後の大きな課題
→ 体験は入り口、“継続可能な暮らし”をどうデザインするかが鍵。
2. 晩茶以外の茶ノ木活用:持続可能性と多様化の模索
上勝町では、古くから晩茶(発酵させた夏摘みの伝統茶)が作られてきましたが、それだけでは経営的にも文化的にも限界が見えています。
そこで、新たな活用法として以下のような試みが進んでいます。
■ 和紅茶の製造
→ 海外紅茶との差別化が可能で、高付加価値化に貢献
■ 茶の実油の搾油
→ 茶葉を摘まない時期の収入源としても期待大
3. 地域に根ざした持続的モデルの構築へ
■ 複業型茶農家という選択
■ 地元住民との共創
→ 地域ぐるみの“共同経営”ともいえるスタイルが今、注目されています。
茶畑は、暮らしの延長線にある“未来”
上勝町のお茶農家が模索するのは、「昔ながらのやり方」を残すことではなく、“どうすれば、この文化が100年後にも山に息づいているか”という問いへの答えです。
暮らしを体験し、茶の多様性を知り、地域と関わる。
その積み重ねこそが、未来につながる新しい茶業の形です。
阿波晩茶はオンラインでもご購入できます♪
オンラインショップ