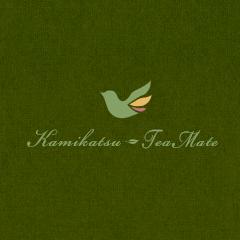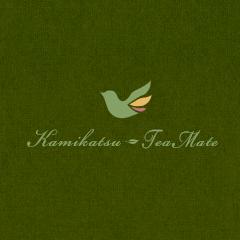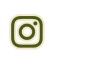皆さんこんにちは!
Kamikatsu-TeaMateの更新担当の中西です!
さて今日は
未来に繋ぐ阿波晩茶〜episode17〜
阿波晩茶は、煎茶や番茶とちがい、乳酸発酵で仕上げる“後発酵茶”。夏の大きな葉を茹でて・揉んで・樽で寝かせて・天日で干す——素材と季節と微生物の共同作業です。ここでは、農園の一年をたどりながら、失敗しない発酵と乾燥の勘どころをまとめます。
1|冬(12–2月):土づくりと来季の骨格づくり
-
剪定・整枝:翌夏に均一な葉を得るため、畝ごとに高さ基準を決めて更新。
-
施肥(基肥):前年の収量・葉色・土壌pH/ECを見て設計。
-
排水・風対策:豪雨溝の通水確認、強風対策の補修。
-
発酵道具の整備:木樽/ポリ樽・重石・竹簀(たけす)・干し場を点検。樽は湯洗い→乾燥→通風保管が基本。
2|春(3–5月):芽吹きの観察と被覆の見極め
3|初夏〜盛夏(6–8月):収穫と“樽入れ”が主戦場
3-1 収穫(刈り取り)
3-2 前処理(茹で・揉み)
-
大釜で茹でる:葉がやわらかく色が鮮やかに変わるまで。
-
水切り→揉捻(じゅうねん):余分な水を切り、葉脈をほぐして菌の足場を作る。
3-3 樽詰め(嫌気発酵)
4|晩夏〜初秋(8–9月):天日乾燥と仕上げ
-
樽明け→ほぐし:塊をやさしく解き、竹簀に薄く広げる。
-
天日干し:からりと晴れた日を待つ。夕立・夜露は大敵なので取り込み動線を先に段取り。
-
乾きの見極め:折ると“パリッ”と音、手触りが軽く、香りが酸×枯れ葉のバランスに。
-
選別・袋詰:茎や極端な欠片を弾き、ロットごとに封緘。遮光・低湿で保管。
5|秋(10–11月):合組と検品
6|発酵を外さないための“現場の心得”
-
嫌気を崩さない:樽詰め直後の空気の道を作らない(押し直しOK)。
-
水切りを侮らない:過多な水分は“においの重さ”に直結。
-
清潔第一:樽と布は年次で総点検。においの移りを避ける。
-
天候待ちの勇気:乾燥は太陽>機械。晴天を狙うほうが結局うまくいく。
7|KPIとトレーサビリティ(簡易フォーマット)
8|よくあるつまずきと処方箋
-
香りが重い → 水切り不足/樽の締めが甘い。次回は揉み後の滞留短縮+詰め直しを徹底。
-
酸が尖る → 発酵温度が高すぎ/期間オーバー。風通しと樽場所を見直す。
-
粉っぽい → 揉みすぎ/乾燥の伸ばし不足。厚みを均一に干す。
阿波晩茶づくりは、畑の段取り×樽の嫌気×太陽の時間。一年の仕事をリズムに乗せ、清潔・記録・天候待ちの三点で外さない。これがうちの答えです。
(見学や体験の受け入れは時期限定。樽入れ期・樽明け期に合わせてご案内します。)
阿波晩茶はオンラインでもご購入できます♪
オンラインショップ